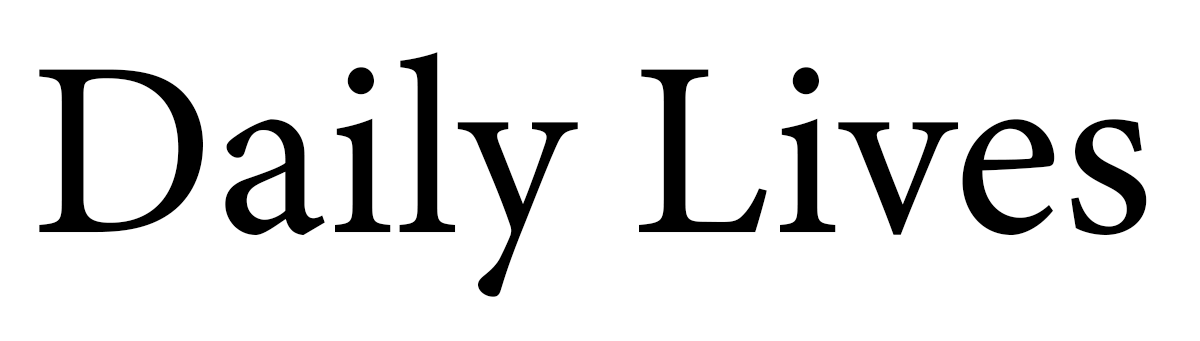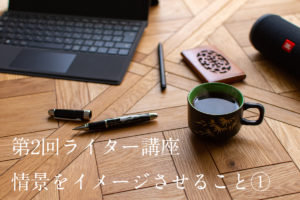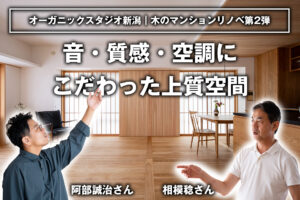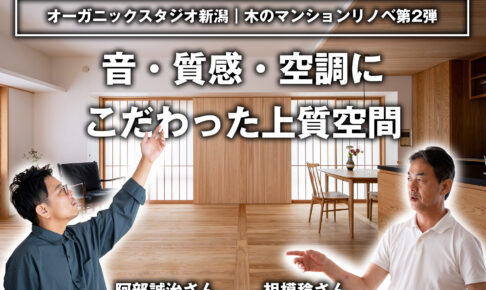久しぶりに「講座」というカテゴリーの記事を投稿します。
「取材の基本」というシリーズで、ライターが取材をする上で押さえておくべきポイントを、備忘録を兼ねて書こうと思います。
今回のタイトル「質問リストの精度を高めれば、すべてが楽になる。」の「楽になる」とは、取材の質を高めながら、スムーズに記事制作を完了できるという意味で、「生産性を高める」と言い換えることもできます。
ちなみに、読者やクライアントが満足できるクオリティの記事を作るのは当然の目標であり、要件です。
今回はそこには言及せず、その要件を満たした上で「ライターの生産性を高めるにどういう準備をして取材に臨むと良いか?」ということについて私見を述べたいと思います。
生産性を高めることは、みんなのメリットになる
やはりプロとして仕事に取り組む以上は、見積もりを出して合意された金額で仕事を進めるわけですが、その見積もり金額の根拠として「どれくらいの時間で仕事を完了できるか?」も当然試算されていなければなりません。
もしも制作物に対して制作時間が長時間化するようでしたら、クライアントがその時間に見合った多くの費用を支払うか?自分自身が時間に見合わない低料金で仕事を請け負うか?どちらかが損をしなければなりません。しかし、どちらかが損をすることで成り立つような仕事が長続きすることはないでしょう。
だから、自身を含めた関係者すべてのために、ライターは生産性を意識しなければなりませんし、ポイントを押さえた心地いいプロセスは制作物のクオリティを高めることにもつながると私は思うのです。
では、ライターの生産性を高めるためにどういう準備をすると良いのか?
押さえるべきポイントは次の4点です。
1.記事の完成イメージを考え、関係者に共有する。
2.質問リストを作り、関係者に共有する。
3.質問リストに沿って取材を行う。
4.質問リストに沿って記事を作成する。
それぞれの項目について解説をしていきます。
1.記事の完成イメージを考え、関係者に共有する。
基本的には、記事の完成イメージは取材前に具体的に思い描き、関係者に共有しておく必要があります。(既に信頼関係が築かれていて、お任せしてもらえる場合はその限りではありません)
雑誌やパンフレットなどの紙媒体でしたら、誌面イメージを作成し、意図や要素が分かるものを渡しておくのがベストです。出版業界で「ラフ」と呼ばれるものです。
インデザインやイラストレーターを使いこなせるとイメージ共有の精度を高められますが、エクセルやパワーポイントも十分に活用できます。(手描きの場合は相手に伝わる表現力やセンスが求められますので、自信がない場合はやめた方がよいでしょう。)
WEBの記事などでレイアウトが限定的な場合は、文章で完成イメージを伝えるので良いと思います。ただ、ダラダラと長い文章を書くのではなく、箇条書きを使いながら誰もが理解しやすい構成にしておく必要があります。
完成形をイメージするためには事前調査が必要になりますが、これだけ情報があふれている時代ですから、事前調査のハードルはかつてと比べてずいぶん低くなったと感じます。
事前調査をして完成形を提案する能力は編集者やディレクターという職業の人は必須ですし、ライターも身に付けておいた方がいいと思います。
2.質問リストを作り、関係者に共有する。
完成イメージができ上がったら、取材対象者への質問リストを作成し、事前に関係者に共有します。
質問項目の数は4~8個くらいが適切だと思います。また、質問項目はなるべくシンプルでありながら具体的であることが重要です。
例えば、質問項目が難解だったり、一つの質問に3つや4つの質問が含まれていると、質問の意図が不明瞭になり、的確な回答がしづらくなります。
シンプルで端的な質問項目を4~8個作ることで、何を聞きたいのかが分かりやすくなります。
そして、もう一つ重要なのが質問項目の順番です。順番を記事の完成イメージと一致させておけば、取材のやり取り自体が一本のストーリーのように展開されて行きます。
そして、明らかな話題の脱線を防ぐこともできますので、密度の濃いインタビューになりますし、後で録音データを聞き直す時間が短縮できます。
3.質問リストに沿って取材を行う。
少し機械的に感じられるかもしれませんが、取材は基本的には質問リストに沿って行うのがベストです。
むしろ最初に「事前にお送りした質問リストに沿ってお話を聞かせて頂きます」と言ってから始めることで、相手は突拍子もない質問が来るかもしれないという不安を感じることが少なくなるでしょう。
もちろん一問一答形式で取材を進めていては話題が広がりませんし、相手も話しづらくなりますので、相手が話した内容について質問を重ねていく必要はあります。
そして、記事を書く上で十分ポイントが押さえられたと感じたら、テンポよく次の質問に進んでいくことで、脱線を抑えることができます。
ちなみに、取材をしていると余談で盛り上がることがありますが、明らかに趣旨から外れる話題が続きそうな場合は、話題を戻す必要があります。
インタビューが一通り終わった後で余談に戻るのが良いでしょう。
4.質問リストに沿って記事を作成する。
取材を終えて記事を作成する段階では、特に問題がなければ伺った話の流れに沿って書き進めます。
質問リストが構成そのものとも言えるので、素直に書き進めれば、自然と流れが分かりやすい記事に仕上がります。
まとめ
以上が、ライターの生産性を高めるための取材準備となります。「質問リストの精度を高めれば、すべてが楽になる。」というタイトルを付けましたが、質問リストとは、骨格にあたるものだと考えています。
取材と記事制作はその骨格に肉を付けていく作業なので、きちんとした質問リストがあってこそ、その肉付けが的確かつ素早いものになるのです。
「事前調査の段階で完成イメージを描かず、取材後に完成イメージを考える方がよい」という考え方もあります。
これは一概に否定するものではありませんが、相応の手間や時間という“コスト”が掛かることを理解した上で、あえてその選択をするべきかどうかを判断する必要があると思います。
また、取材を終えてから記事の方向性を変更する必要性が出てくることもあります。
その時は軌道修正をして完成形を変えればよいと思います。その場合も、何もイメージを持っていない状態よりも、あらかじめ完成イメージを持っている状態の方が、的確な軌道修正がしやすくなると思います。
取材現場では、その場に立ち会うすべての人の“時間”というコストが投入されています。
その貴重な時間をなるべく無駄なものにしないためにも、精度の高い質問リストを用意する必要がありますし、それが関係者への誠意や配慮でもあると思うのです。