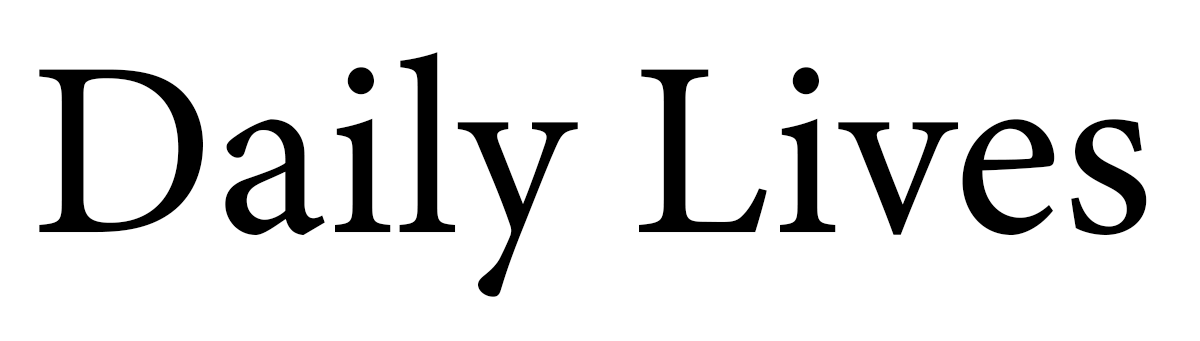2014年7月29日~30日。私は妻と一緒にトルコ南東部の街・マラティヤ(Malatya)にいた。

トルコを8日間ほどかけて周る新婚旅行の途中で、トルコ南東部の街・マルディン(Mardin)から半日ほど掛けてこの街に到着した。
特にマラティヤに行きたかったわけではなく、マルディンからカッパドキアまでバスで移動するための中継地点として1泊することにしていたのだ。

トルコではどこに行っても親切にされた。チャイ屋に入ればチャイをおごられ、ピザ屋の前を通りかかれば、店主からピザをもらったりもした。お金を払おうとしても受け取らない。

はるばるトルコを訪れた東洋人をもてなしたいという気持ちの現われなのであろうか。優しさが心にしみた。

マラティヤに何があるのか私たちは知らなかった。夕方に街に到着し、その翌日の午前中にはカッパドキアに出発しようと思っていたくらいだから、特に調べもしていなかった。

宿泊したホテルは「DOUBLE TREE by Hilton Malatya」(今は名前が変わって「Mövenpick Malatya Hotel」になっている)。フロントのホテルマンはとてもスマートで礼儀正しく温かかった。洗練されたデザインのラウンジや、5つ星ホテルらしい抜け目のない客室で、私たちは旅の疲れを癒やすことができた。
翌朝午前中にカッパドキア行きの長距離バスに乗るつもりでいたが、午前中は予約がいっぱいでその日の夕方出発のバスになってしまった。
予定外に夕方までマラティヤで過ごさなければならなくなった私たちは、ガイドブックを見て博物館に行ったり、モスクを見たり、街を散策して過ごしたりした。

マラティヤはそこそこ大きな地方都市ではあるが観光地ではない。そのため、外国人旅行者は少なかった。
だからこそ、素顔のトルコがあり、街歩きをするのが楽しかった。
私たちが集合住宅があるエリアを歩いていると、人の良さそうな地元のおじさんが声を掛けてきた。

英語ではなくトルコの言葉を使っているので、何を言っているのかは分からないが、察するに「私の家がすぐそこだから是非チャイでも飲んでいってくれ」ということのようだった。
私たちはおじさんに従って目の前の集合住宅の階段を上がり、案内された2階の部屋へと入っていった。
おじさんは家にいた奥さんに「日本から来たお客さんを連れてきたよ。チャイを振る舞ってくれ」というようなことを言い、私たちをリビングに案内してくれた。
なんと、そこでチャイだけでなく、パンやチーズ、野菜などを出してお昼ごはんを振る舞ってくれたのだ。

なぜ見ず知らずの旅行者にここまで親切にしてくれたのか分からなかったが、ただ中継地点として立ち寄ったこの街がとても印象的な場所に変わった出来事だった。
共通の言語を持たない私たちだったが、不思議と楽しい時間を共有できた。
そろそろ出発すると言って立ち上がると、おじさんは「そうか、もう行くのか」というような少し寂しそうな表情を浮かべながら私たちを見送ってくれた。

それが私のマラティヤの思い出だ。
それから8年半の月日が流れた2023年2月6日、テレビで「トルコ・マラティヤ」の文字と共に現地の映像が映し出された。砂埃が舞う街で建物が崩壊する映像だった。逃げ惑う人々。悲鳴が聞こえてくる。まるでパニック映画だ。
私が記憶していた、明るく平和で活気に満ちた雰囲気はない。地震の圧倒的な力が、紛争や戦争以上に人の命も自由も尊厳も全てを奪い去ろうとしていた。
どうか、親切にしてくれたマラティヤの人々が無事であるように…と願わずにはいられない。
とてもショッキングな映像が連日流れてくる。がれきの中から人々が助け出され歓声が上がる。小さな赤ちゃんや子どもが助け出されるのを見てはホッとする。
その一方でニュースで伝えられる死者数は毎日増えていく。現地では地獄のような時間が流れ続けているのだ。2011年の東日本大震災を思い出す。
微力ながら私にできる支援はなんだろうか?と考えたが、募金しか思いつかなかった。
しかし、いくら募金をしたらいいのか私には分からなかった。
私がたとえ全財産を募金したところで、その影響はたかが知れている。それよりは、少額ずつでも毎日長く続ける方が大事なのではないかという考えに至った。
私はスーパーやコンビニで買い物をするたびに小銭を募金箱に入れることを決めた。
今日募金箱に入れたお金が、現地の赤ちゃんのオムツや粉ミルクになるかもしれないし、がれきを動かす重機の燃料になるかもしれない。チャイを飲みながらリラックスした時間を過ごすのに役立つかもしれない。
私がレジ横の募金箱に小銭を入れる行為が、周囲の人が募金をする動機付けに多少はつながるかもしれない。

わずか8日間程の旅行だったが、毎日とてもたくさんの親切に触れた思い出深い国だった。
次にまたトルコ旅行に行ける日がいつになるかは分からないけど、また旅をしてみたい。
今は少しでも彼らの支援になればと願いながら、募金をなるべく長く続けていきたいと思う。